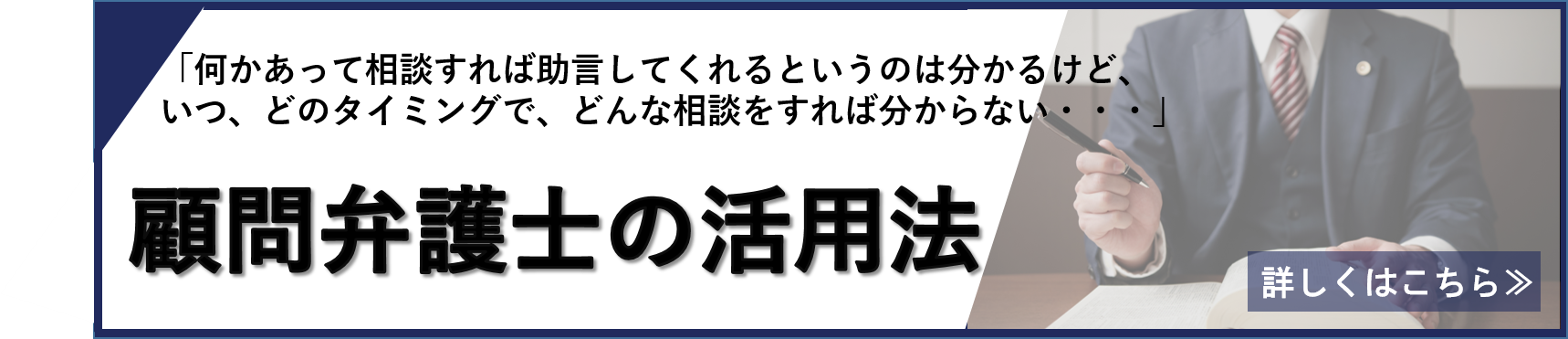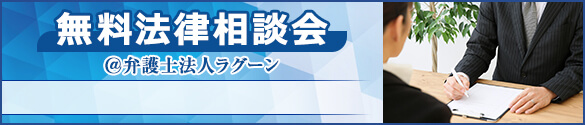同一労働・同一賃金の原則(定年退職後)
1 はじめに
いわゆる同一労働同一賃金の原則(以下、「本原則」と言います。)が法制化され(パートタイム労働法第8条、労働者派遣法第30条の3及び同条の4)、本原則への対応は不可避となってきています。
この原則に違反した賃金設定を行った場合、会社は「通常の労働者」の賃金との差額を遡って損害賠償させられることになります。たとえば、通常の労働者であるAさんには月2万円のX手当を支給し、Aさんと同一の労働をするBさんにはX手当を支給しないという運用を2年間ほどしていたところ、かかる待遇差が違法とされた場合、2万円×24カ月=48万円を賠償しなければならなくなります。
このような事態を避けるためには、本原則に違反しないようにするほかないのですが、条文の文言をご確認いただけると分かるとおり、非常に抽象的かつ曖昧な規定で、具体的にどのような場合に違法と判断されるのか読み取れません。
そこで、ここでは、判例から具体的にどのようなケースで裁判所が違法の判断を下しているのかを解説します。
なお、本原則に反するかどうかの判断は、類型的に①定年退職後再雇用された者と通常の労働者との比較、②定年退職前の有期労働者等と通常の労働者との比較、に分けて行われているといえます。本頁では、類型①に絞って解説します。
2 判例紹介
代表的なものとして、法律解説のきっかけとなった最高裁判例である「長澤運輸事件」についてご紹介します。同判例における事実関係は、概ね以下のとおりでした。
<事実関係 開始>
1 当事者
(1)原告X: Y社を定年退職し、期間の定めのある従業員としてY社に継続雇用された。
※ 実際の原告は3人ですが、代表して1人を挙げています。
(2)被告Y: 輸送業を営む株式会社。従業員総勢66人。
2 労働条件関係
(1)Xの職務等
定年前後で変わらず、バラセメントタンク車の乗務員として稼働(職務内容に変更なし。)。
正社員と同様に、勤務場所及び担当業務の変更があり得た。
(2)定年 満60歳(以後は「嘱託者」とする。)
(3)定年後の就業規則の適用
嘱託者には一部適用しない。別に、嘱託社員就業規則あり。
(4)Xの雇用期間 1年(但し、更新あり)
(5)Y社の賃金
ア 正社員(無期雇用労働者)
(ア)基本給
在籍給 在籍1年目が8万9100円で、以降1年ごとに800円を 加算。但し、上限12万1100円。
年齢給 20歳を0円として1歳ごとに200円加算。但し、上限6000円。
(イ)能率給 10tバラ車 月稼働額×4.6% ・・・以下、省略
(ウ)職務給 10tバラ車 7万6952円 ・・・以下、省略
(エ)精勤手当 所定労働日全ての日に出勤した者に対して月5000円
(オ)無事故手当 1月無事故の者に対して月5000円
(カ)住宅手当 一律月1万円
(キ)家族手当 配偶者5000円、子1人当たり5000円(上限2人)
(ク)役付手当 班長3000円、組長1500円
(ケ)超勤手当 法定時間外労働に対する割増賃金
(コ)通勤手当 公共交通機関1月定期代相当額(上限4万円)
(サ)賞 与 組合との間で年間賞与を基本給の5カ月分と定めた
(シ)退職金 3年以上勤務した者に支給する。
イ 嘱託社員(定年後の有期雇用者。本件におけるXの場合)
(ア)基本賃金 月12万5000円
(イ)歩合給 12tバラ車 月稼働額×12% ・・・以下、省略
(ウ)無事故手当 月額5000円
(エ)調整給 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始までの間、月額2万円
(オ)通勤手当 公共交通機関1月定期代相当額(上限4万円)
(カ)時間外手当 法定時間外労働に対する割増賃金
(キ)賞 与 なし
(ク)退職金 なし
※ これによると、Xの年収は定年前の79%程度になることが予想された。
※ 労働組合との交渉の結果、上記条件となった。
3 時系列
平成26年9月30日 XがY社を退職。
XはY社から退職金12万1500円の支給を受けた。
同 日 XがY社と有期労働契約を締結。
<事実関係 終了>
Xの訴えは、①嘱託社員には能率給及び職務給は支給されず歩合給が支給されること、②嘱託社員には精勤手当、住宅手当、家族手当及び役付手当が支給されないこと、③嘱託社員の時間外手当が正社員の超過手当よりも低く計算されること、④嘱託社員に賞与が支給されないことが、(当時の)労働契約法第20条に反するとして、これらの不支給分の支払いを求めるものでした。
この訴えに対し、裁判所の判断は、総論として、①使用者は、経営判断の観点から、労働者の職務内容及び変更範囲にとどまらない様々な事情を考慮して賃金に関する労働条件を検討するものということができる、②定年退職後に再雇用される有期契約労働者は、定年退職まで無期契約労働者として賃金の支給を受けてきた者であって、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給も受けることができるのであるから、この点は賃金に関して考慮してよい、③複数の賃金項目がある場合、賃金項目ごとに支給の趣旨が異なるのであるから、不合理性の判断においては、賃金項目ごとに各賃金項目の趣旨を考慮すべきである、との判断を示しました。
そして、各論的な判断として、Xの訴えに対して以下のような判断を示しました。
(1)能率給及び職務給がない点について
結論 不合理ではない
理由 基本賃金は定年前の基本給を上回っているし、歩合給の係数は能率給の係数の約2~3倍に設定されており、労務の成果が
賃金に反映されやすいように工夫がなされている。
労働組合との協議の結果として決められたものである。
正社員と比べて10%程度低いにとどまる。
(2)精勤手当がない点について
結論 不合理である
理由 正社員と嘱託社員とで皆勤を奨励する必要性に相違はない。
(3)住宅手当及び家族手当の支給がない点について
結論 不合理ではない
理由 福利厚生及び生活保障の趣旨で支給されるものである。正社員の 場合、嘱託社員と異なり、幅広い世代の労働者が
存在し得るのであるから、住宅費及び家族を扶養するための生活費を補助することには相応の理由がある。
他方で、嘱託社員の範囲は限定的であるし、老齢厚生年金の支給や調整給の支給もある。
(4)役付手当の支給がない点について
結論 不合理ではない
理由 役付手当は、その支給要件及び内容に照らすと、正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるものといえる。
(5)時間外手当と超勤手当の相違について
結論 不合理である
理由 嘱託社員に精勤手当が支給されないのは不合理であるから、法定労働時間外労働の割増賃金の基礎賃金に精勤手当が
含まれていないのもまた不合理である。
(6)賞与の支給がない点について
結論 不合理ではない
理由 賞与は多様な趣旨を含み得るものである。嘱託社員は老齢厚生年金の支給、調整給の支給を受けられること、
年収の減額は79%にとどまると想定されること等を総合考慮すると、不合理とまではいえない。
(7)最終結論 Xに9万円支払え、時間外手当は差戻し。
最高裁は、同一労働同一賃金の原則について、職務内容及び変更範囲以外の事情も考慮して合理性を判断することを明らかにし、定年後再雇用の労働者については定年まで無期雇用労働者としての待遇を受けてきたことや老齢厚生年金の支給があることを考慮して、全体としてやや緩やかに合理性の判断をしたものと評価することができます。
また、合理性の判断を賃金項目ごとにその趣旨を考慮して行うという判断方法を明らかにしたのは特筆すべきことです。
一方で、基本賃金、歩合給、基本給、能率給及び職務給の判断において、基本賃金及び歩合給と基本給、能率給及び職務給を比べて場合に前者は後者よりも⑩%低いにとどまると指摘されていますが、「それでは一体どの程度の減額までは許容されるのか」という点については未だに明らかになったとはいえない状況が続いています(一概には言えませんが、複数の裁判例を分析すると、概ね10~30%程度の減額であれば違法と認定される可能性は低く、50%以上減額すると違法と評価される可能性が高く、30~50%がグレーゾーンといった印象です。)。
3 対策
(1)まずは現状の確認を
まずは、自社の定年後有期雇用労働者の職務内容及び変更範囲等が定年前と比べてどのように変化しているのかを確認することが必要です。
次に、職務内容及び変更範囲が定年前後等で変わっていない(又はほとんど変わっていない)場合、各賃金項目を確認します。各賃金項目がどのような趣旨で支給されているのかを確認し(実際には、裁判所からどのような趣旨で支給されているものと認定され得るかという法的評価も必要です。)、その趣旨に照らして定年前の正社員と定年後の有期雇用労働者との間で差異を設ける合理的な理由があるかどうかを検討します。
また、福利厚生的要素の賃金ではなく、労務の対価的性格の強い賃金について、定年前後の減額幅を確認します。
(2)対応
ア 労働条件を変える
本原則は、根本的に「同一労働」であることから問題となる原則なので、①職務の内容、②仕事の責任、③職務変更・勤務地変更の有無など、労働条件に明確な差を設ければ違法の評価を受ける可能性は低くなります。
一般論として、仕事の内容を正社員の補助的な業務とし(①)、ノルマ及びノルマ不達成の場合の賃金減額などの設定を行わず(②)、職務変更・勤務地変更はしないとすれば(③)、よほど賃金を減額しない限り、本原則に反することにはならないといえます。
これら労働条件の差は、雇用契約書、就業規則(賃金規程等を含む)などに明記されなければなりません。したがいまして、併せて、これらの改訂作業も行うことになります。
イ 減額幅・手当項目を変える
どうしても定年退職後の労働条件を変えられない(人的余裕がない)場合には、上記判例に照らして差を設けることが違法と評価されそうな手当については削除又は変更します。最終的には、基本給など労働対価的性質を持つ賃金と各種手当を併せて定年前からの減額幅を10~30%程度に収めることができれば、違法と評価される可能性は低くなります。
なお、賃金規程を変更する場合、就業規則の不利益変更(労働契約法第10条)の問題が生じることがありますので、改訂作業の際には法律専門家の助言を得て行った方がよいでしょう。