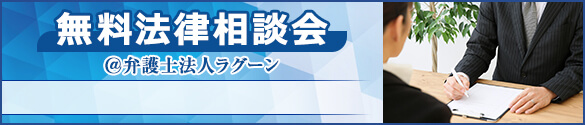第62回メルマガ記事「雇用契約と賃金の基礎」2021.3.25
弁護士の内田です。
暖かくなってきましたね。下関では桜が満開です。ですが、まだまだ花見・・・という雰囲気にはなっていません。
1日も早く新型コロナウイルスの影響が終息することを願うばかりです。
新型コロナウイルスの影響が終息した後も、今の「人とあまり会わない習慣」はある程度継続するのではないかと言われています。
新型コロナウイルスが流行り出して、「初めからオンラインで行っていればよかった。」と判明した業務が多くあると思います。そのような業務はこれからもオンラインであり続けるでしょう。
私たちの属する法曹界でも、裁判所に行って「陳述します。」と言いに行くだけの業務など、「オンラインでよくないですか?」と思う業務が多々あります。
他方で、「オンラインでも出来るけど、やっぱり会った方がいいよね。」と思う業務もあります。従業員向け勉強会などがそれです。
私は、ZOOMなどを使って従業員向け勉強会を開催しているのですが、webだと受講者の表情などが読み取れず、「ここはもう少し噛み砕いて説明した方がいいな。」「ここは皆さん分かっているようだから駆け足でいいな。」などの調整が難しいです。
これからは、新型コロナウイルス時代前に比べて「リアルで会う意義」が厳しく問われる社会になってくるのでしょう。
さて、本日のテーマは「雇用契約と賃金の基礎」です。
本メルマガを読まれている方には「雇用している人」も「雇用されている人」もいらっしゃるかと思いますが、意外と「雇用契約ってどういう契約?」と問われると的確に答えられないものです。
今回は、雇用契約の本質的なところから賃金の取扱いに関する法制について基礎的なところを解説しようかと思います。
雇用契約の本質を最も端的に表しているのが民法第623条です。条文は以下のとおりです。
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
会社と従業員という表現の方が分かりやすいかと思いますので、会社・従業員という表現で説明します。雇用契約は、従業員が会社に対して労務を提供することを約束し、会社はその労務に対して賃金を支払うことを約束する契約ということになります。
たったこれだけのことですが、このことから重要な原理原則を導くことができます。
会社は労務の対価として賃金を支払うことを約束しているわけですから、従業員が働かなければ会社は賃金を支払わなくてもよいというのが原則になります。これを「ノーワークノーペイの原則」と言います。これが大原則です(働かなければお金はもらえないという当たり前のことではあるのですが・・・)。
労働基準法等によりこの原則は修正を受けていますが、これが大原則であることは押さえておく必要があります。
修正要素として新型コロナウイルスの関係で問題となるのは、労働基準法第26条と民法536条です。この2つの条文の関係が非常に分かりづらくなっています。条文は以下のとおりです。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
このうち、先ほどノーワークノーペイの原則を端的に表しているのが民法第536条第1項です。言葉が難しいので分かりづらいのですが、「当事者双方の責めに帰することができない事由」=天災などの不可抗力、「債務を履行することができなくなったとき」=労働者が労務を提供できなくなったとき、「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」=会社は賃金の支払いを拒むことができる、と読み替えていただけると分かりやすいかと思います。
要は、会社・従業員のどちらのせいでもなく労務提供ができなくなった場合には、労務の対価である賃金の支払いもしなくてよいですよ、ということです。正に、ノーワークノーペイの原則ですね。
ただ、従業員にとって賃金は生活の糧ですから、ノーワークノーペイの原則を貫くと従業員の生活が困窮する場面が多くなってきます。そこで、従業員保護の観点から労働基準法第26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」に限り、従業員が労務の提供をしなくても会社に平均賃金の6割を支払うよう規定しています。ここでいう「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」は広く「会社側の都合で」という意味で理解されており、「取引先の都合で資材が届かず、予定していた工事できなくて、やむなく従業員を休業させた。」というような場合もこれに該当します。
感のよい方は気付かれたかもしれませんが、民法第536条第2項にも同じような言葉が使われています。しかし、この条文の「債権者の責めに帰すべき事由」は上記の「使用者の責に帰すべき事由」とは異なり、「会社に故意・過失又はこれと同視すべき事由がある場合」と限定的に理解されています。
たとえば、会社が従業員を不当解雇して当該従業員の労務提供を不可能にしたという場合がこれに該当します。このような場合は、会社は、契約どおりの100%の賃金を支払わなければなりません。
簡単に整理すると、①会社も従業員のどちらにも全く落ち度はないけど、仕事ができなくなった場合=賃金の支払義務なし(民法第536条第1項)、②会社も従業員のどちらにも落ち度はないのだけれども、どちらかといえば会社の都合で仕事ができなかったといえる場合=平均賃金の60%に限り、賃金の支払い義務を負う(労働基準法第26条)、③会社の落ち度で従業員は労務提供ができなくなった場合=100%の賃金支払義務あり(民法第536条第2項)、ということになります。
このような整理を前提として、次に新型コロナウイルスに関連した賃金問題を考えていきましょう。なお、最高裁判例等が出ているわけではなく、100%こうなるということではありません。
このようなケースについて考えてみましょう。
ある従業員が朝の検温で38度、咳の症状も見られていたとします。さらに、3週間前に接触していた親族が新型コロナウイルスに罹患していたことが判明していたとします。しかし、当該従業員は「仕事に支障はない。就業を拒否するなら賃金は払え。」と言っていたとした場合、会社に賃金の支払義務はあるのでしょうか。
結論として、賃金の支払義務はありません。労務を提供できるかどうかは「社会通念」によって判断されます。これは「常識的に」と読み替えていただいて結構です(究極的には裁判官の考える常識的なところ、ということになります。)。つまり、このような新型コロナウイルスの症状が見られ、新型コロナウイルスに感染している可能性が濃厚な者については、他の従業員にも感染させる危険性があるため、いくら仕事はできるとしても「社会通念上労務提供は不可能」と判断されるわけです。
難しいのは、「東京などの感染者数が多い場所に行って帰ってきた従業員」など、新型コロナウイルスに感染している可能性が若干高いくらいの従業員の取扱いです。このような従業員に対して休職を命じて賃金を支払わないという対応が許されるのかという問題です。
何の合理的根拠もなく休職させた場合、民法第536条第2項により会社は従業員に対して100%の賃金を支払わなければなりません。他方、ある程度の根拠があって自社従業員への感染拡大防止の観点から休業させたのであれば、同項の適用はなく、労働基準法第26条に基づき平均賃金の60%を支払えば足りるでしょう。
上記のケースについて考えると、「東京に行った。」という程度では感染していると疑うに足りる合理的理由があるとはいえませんので、賃金は100%支払わなければならないといえます。しかし、これに加えて、「東京から帰ってきて2週間後から37.5度前後の微熱が続き、しばしば咳もしている」というような事情も見られると、感染を疑う合理的理由はあるといえますから、感染予防の観点から休職させても平均賃金の60%の支払で足りることになると考えられます。
実際には、「陽性者が出た飲食店で、陽性者がいた場所からは5メートル程度離れたところで飲み食いをしていた従業員」といったケースのように、上記①~③のどの対応を選択してよいのか迷うことも多いです。
このような場合、中間的な対応である②を選択して平均賃金の60%を支払うという対応をすることが無難な場合が多いでしょう。
いかがだったでしょうか。
法律は一見すると難しいものですが、本質的なところから理解していくと分かりやすいものです。
雇用契約は企業活動に必須の契約ですから、しっかりと本質的なところから理解しておいた方がよいといえるでしょう。