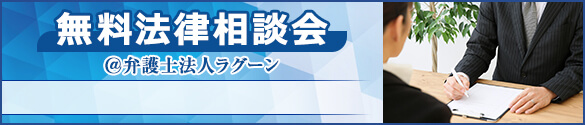「コンサルティング契約書」の注意点について
1 コンサルティング契約の特徴
コンサルティング契約の特徴は、①一定の結果を保証するものではないこと、②業務の内容が不明確になりがちであること、の2つです。
依頼者からすれば高いコンサルティング料を払っているのだから一定の結果は保証して欲しいと思いますし、広告物の作成などの作業はコンサルティング会社側で行って欲しいと考えます。他方、コンサルティング会社側はアドヴァイスを受けた後の実行は依頼者側に依存しており、また予想し得ない事情の発生は避けられないことなどから100%の結果保証は出来ないと考えます。また、コンサルタント料の対価は知識であって肉体的な労働ではないと考えて、広告物の作成などの「作業」はあまり負担したくないと考えているかもしれません。
物の売買とは異なり、コンサルタント契約は代金(フィー)とその対価たる商品(又は役務)の関係が不明確なので、上記のような当事者の考え方の違いから紛争になることが少なくありません。依頼者「コンサルタント料を払っているから〇〇まではコンサル会社の方でやってくれ」、コンサルタント会社「いえ、〇〇は別料金になりますのでお受けできかねます。」というように業務の内容・範囲などを巡って争いになるのです。
その他、情報の正確性確認義務といった比較的めずらしい条項などのほか、旅費日当、機密保持、損害賠償などの一般的な条項も当然問題となりえます。
以下では、具体的に実務で使用されているコンサルタント契約書をベースに解説していきます。
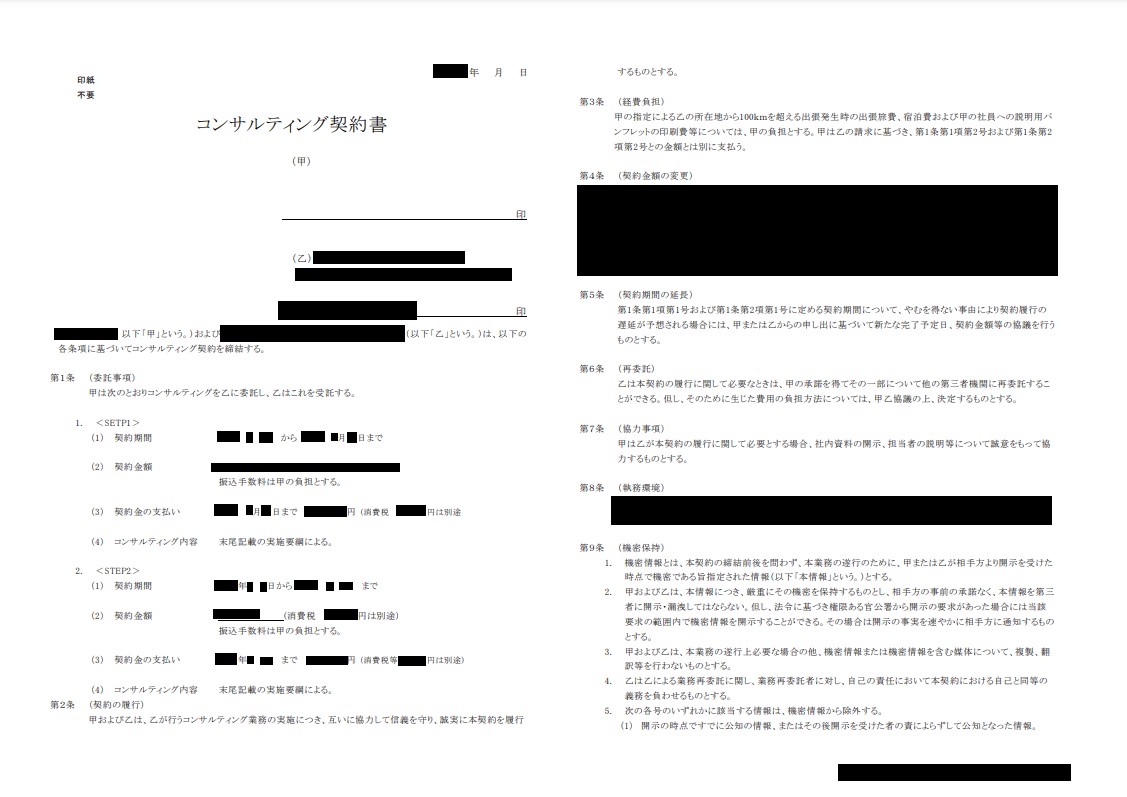 |
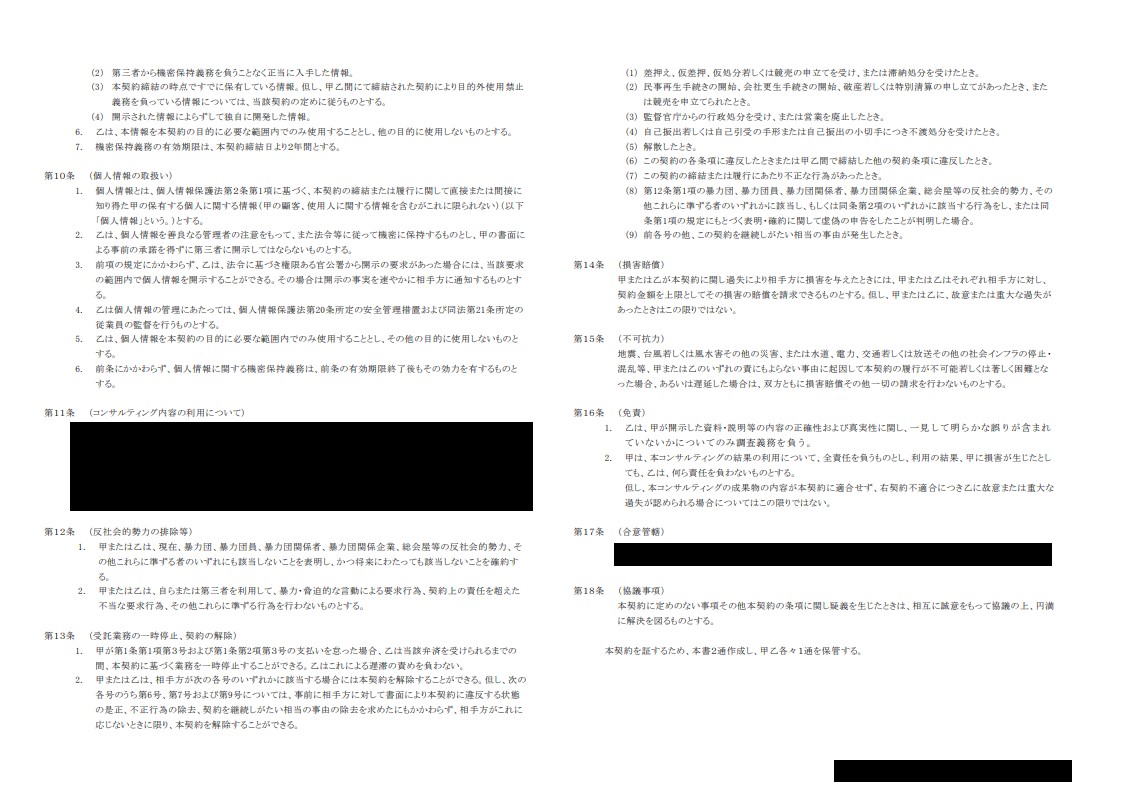 |
 |
2 各条項の解説
(1)業務の内容・範囲
上述のとおり、コンサルタント契約では、代金の対価たるコンサルタント業務の内容・範囲に関する認識の違いにより紛争となることが多いです。
本契約書では、第1条第1項4号の「コンサルティング内容」でコンサルタント業務の内容・範囲が定められていますので、この条項に従い末尾の「実施要綱」を見てみることになります。実施要綱には「乙の提供する業務」欄がありますが、そこに記載があるのは「業務状況把握支援」「運用マニュアル・手順書整備支援」で極めて曖昧です。これでは、コンサルタント会社側が具体的に何をすることを約束してくれているのかほとんど分かりません。
とはいえ、コンサルタント会社が提供する役務を詳細に記載していると契約書が分厚くなり、読みづらくなるという実務上の問題もあり、「その他備考」欄に記載のとおり「詳細は●●●●付提案書の通り」として別にコンサルティング業務の内容を特定する資料を添付することが多いです。
まれに、コンサルティングレポートなどの成果物の交付について記載がない場合や、相談等に対応してくれる時間帯・人数などの記載が抜けている契約書も散見します。これらは契約書に十分記載可能な内容ですので、抜けているようであればきちんと記載してもらうことが必要です。
(2)情報の正確性確認義務
本契約書で情報の正確性確認義務を定めているのは第16条です。本契約書ではコンサルタント会社は依頼者から提供された情報について「一見して明らかな誤りが含まれていないか」のみ調査義務を負うとされており、基本的に依頼者側に提供資料の正確性調査義務が課されています。
コンサルタント会社側は一切の調査義務を負わないとする契約書も多いので、依頼者する側はよく確認しておいた方がよい条項といえるでしょう。
(3)旅費日当実費
本契約書だと第3条が旅費日当実費について定めていますが、その計算方法や上限などが不明確になっています。
依頼者とコンサルタント会社間の距離が遠い場合には、予想外に旅費日当実費が高額になることもありますので注意が必要です。
(4)機密保持
本契約書だと第9条が機密保持を定めています。コンサルティング契約では、依頼者はコンサルタント会社にセンシティブな情報を提供することが多いので、ほとんどの場合、機密保持条項が入ります。
機密保持条項は定型的な内容であることが多いのですが、有効期間については提供する情報の種類によって異なっています。時の経過と共に陳腐化して価値を無くすような情報だけを提供するのであれば数年と定められますし、依頼者側の事情によっては永続と定められることもあります。
(5)損害賠償
本契約書で損害賠償の定めをしているのは第14条です。特徴として、「故意又は重大な過失」の場合を除き、賠償金の上限が契約金額に限定されています。このような条項はITシステム関連の契約書でも散見されます。
民法の原則的ルールに従えば、賠償金にこのような上限はありません。その意味で、依頼者側に不利になる条項といえるでしょう。ただ、コンサルティングという業務の性質上、多額の賠償問題になることも少ないためか(勿論、業務の内容にもよりますが・・・)、実務上はあまり問題視されていないようです。
依頼者側としては、コンサルタント会社に多額の賠償を求めることはできないということを前提に、別のリスクヘッジ策を講じておく必要があるといえるでしょう。