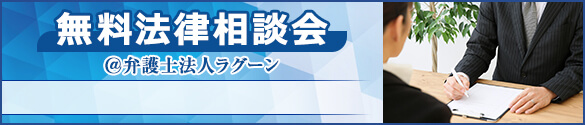第85回「労務における手続保障」
弁護士の内田です。
仕事をしていると新しい商品・サービスの設計・開発をしなければと思うことが度々あるのですが、机に座ってパソコンと格闘していても良いアイディアは生まれないものです。
商品開発に関する書籍なども読むのですが、曖昧なことがばかり書いてあって、中々具体的アイディアに辿りつけません。
商品開発部門で働かれている方々は大変すばらしいと思うわけですが、特にその中ですごいなと思うのは「幼児向け商品」の開発部門で働かれている方々です。
と言いますのも、我々は「大人」ですから、「大人」が欲しがるものは何となく分かります。ですが、幼児のときの記憶なんてありませんから、幼児に「ウケる」ものなどどう頭をひねっても出てきません。おしり探偵のような発想は一生考えても出てこないでしょう。
いつか機会があれば、是非、幼児向け商品の商品開発部の方から話を聴いてみたいものです。
さて、本日のテーマは「労務における手続保障の重要性」です。
労務問題では、どうしても実体(内容)面の方にばかり目を奪われるのですが、それと同じくらい重要なのが「手続」面です。
司法は、内容の正しさは手続によって担保されるという考え方です。
民事訴訟も刑事訴訟も主張されている内容の誤りを確認する手続だと表現することができます。
このような考え方は度々判例の中に現れています。
たとえば、就業規則の不利益変更による労働条件の変更における合理性(労働契約法第10条)の判断や解雇の合理性・相当性の判断において、労働者の言い分・事情を聴き取る手続を行ったかどうかが重視されています。
懲戒処分でいえば、労働者に弁解の機会を与えた上で処分した場合とそれを与えないで処分した場合とでは、圧倒的に前者の方が処分の有効性(≒合理性・相当性(労働契約法第15条))が認められやすくなります。
この点を踏まえると、会社が労働者に対して何らかの不利益な処分を課す場合には、会社は労働者に対して言い分・事情を述べる機会を与えて、それを証拠化しておくべきということになります。
ポイントは「機会」で足りるということです。機会を与えたにもかかわらず労働者がそれを放棄した場合(たとえば反論・言い分を書面で提出するように求めたにもかかわらず提出しないなど)には、会社の判断で処分を進めるしかありません。
近時、会社から配転命令(転勤)を受けた労働者が介護の必要な親族が存在したにもかかわらずそのことを会社に回答しなかった点に触れ、そのような場合には配転命令の有効性は会社が認識していた事情を基に判断する(介護の必要な親族が存在するという事情は考慮に入れない)とした裁判例が現れました(大阪地裁令和3年11月29日判決)。
会社に対して主張できる事情があり、かつその機会が与えられていたにもかかわらずそれを主張しなかった場合には、その事情が考慮されないという不利益を受けてもしょうがないという考え方だといえるでしょう。
なお、上記裁判例は結果として配転命令を有効と判断しています。
当然ですが、民事訴訟でも主張していない事実は認定されないルールになっています。その意味では、上記裁判例は裁判制度に整合した判断を示したものといえるでしょう。
ここまでの話からすると、ともかく労働者に対する手続保障は厚くした方がよいのでないかという考え方が出てきます。たしかに手続保障は厚いほどよいのですが、手続保障を厚くするほど会社の総務コストは高くなります。そのた、め、就業規則等で定める会社のルールにおいては、手続の選択について柔軟性をもたす必要があります。
よく拝見するいかがなものかと思う例が「懲戒委員会」(「賞罰委員会」という名称であることもあります。)です。「懲戒処分を課す場合には懲戒委員会を開催して議決する。懲戒委員は、代表取締役、法務部長、・・・とする。」のような規定です。
このような規定があると懲戒処分をする際にいちいち社長や重役の時間を拘束して委員会を開催しなければならなくなります(就業規則で定めてしまうとそれが労働条件の一部となるので、懲戒委員会を経ないでした懲戒処分は無効になってしまいます。)。ですが、たとえば戒告や譴責といった軽い処分を課す場合にまでそこまでの手続が必要になることは少ないですし、防犯カメラ等の客観的証拠によって非違行為が明らかな場合なども同様です。事案に応じて然るべき手続保障を行えればよく、懲戒委員会は必須ではありません。
手続保障は法律的に重要ですが、総務コストとの関係ではトレードオフの関係にあるため、バランス・メリハリが大切になります。大企業が用意すべき手続保障のレベルと中小企業の用意すべきそれは違います。
自社の規模・人員体制等に鑑み、適切なルールを定める必要があります。
労務に関する手続でもう1つ重要な点としては、懲戒処分を課す順番が挙げられます。
懲戒処分は、原則として①戒告(譴責)⇒②減給⇒③出勤停止⇒④降格⇒⑤諭旨解雇⇒⑥懲戒解雇、というように軽い方から課していきます(③④は内容によって前後するでしょう。)。これは、必ず①から⑤(⑥)まで全てという意味ではなく、重い処分をする前には先に軽い処分をしておかなければならないという意味です。
判例・裁判例の傾向を見ると、いきなり重い処分を課してしまうと「重きに失する」とか「会社も十分に指導していたとはいえない」「改善の機会を与えていたとはいえない」などという理由で無効になってしまうことがあります。ですので、まずはちゃんと戒告や減給といった軽い懲戒処分を課すことによって指導と改善の機会を与える必要があるのです。
実は、このように「まずは軽い処分を」というのは刑事裁判の考え方に馴染みます。1回目の万引きで実刑になることはほとんどありませんが、罰金⇒執行猶予付判決⇒実刑と回を重ねるごとに制裁は重たくなっていきます。
不利益な処分を受け十分更生する機会が与えられていたにもかかわらず犯罪を繰り返したのだから、重い処分を受けるのはやむを得ないという考え方です。こういった考え方が懲戒処分においても準用されているといってよいでしょう。
本日の話を整理すると、労務において重要な手続は①弁解の機会を与える、②反省・改善を促すためにまずは軽い処分をする、の2つということになります。
本メルマガを機に、自社の手続運用が上記の2点を守っているか否かについて点検されてみてはいかがでしょうか。