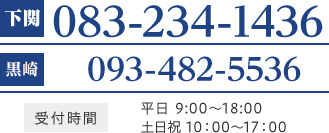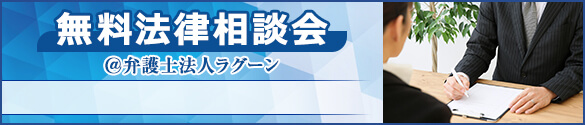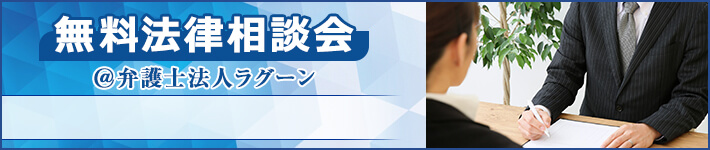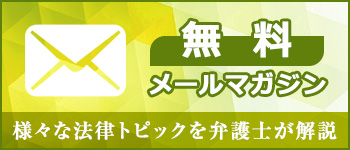第117回 君子危うきに近寄らず
弁護士の内田です。
おかげさまで当法人の顧問先企業様が100社を超えました。
通常、自分の所属する会社の業界にしか詳しくならないと思いますが、弁護士をやっていると様々な業界の会社様から相談を受けるため、多くの業界に詳しくなります。
訴訟等には必要でない情報であっても、せっかくの機会なので業界話はお聞きするようにしています。
そうして10数年、今は一般の方よりもちょっと利口に買い物ができるようになったように思います。
自分の業界以外にも視野を広げることは大切ですね。
さて、今回のテーマは、「君子危うきに近寄らず」です。要するに、民事と刑事の話になります。
繁華街で酔っ払いに殴られた、詐欺会社に会社の金を騙し取られた、というように事案によっては民事問題と刑事問題が同時に生じることがあります。
では、法律上、民事と刑事はどのような区分けになっているのでしょうか。
結論から言いますと、民事と刑事は全く別ものです。
たとえば、「繁華街で殴られた」という事案でいいますと、民事上は不法行為(民法第709条)ということになり、民事法廷で加害者の行為が不法行為に該当するか、賠償額はいくらか、ということが審理され、判決としては「被告は、原告に対し、金30万円を支払え。」みたいな判決が出されます。犯罪に該当するのかという点は審理されず、専ら「不法行為」に該当するかどうかだけが審理されます。なお、民事では訴えられた方を「被告」と言います。
民事訴訟で勝訴判決を得ても、国が賠償金を払ってくれるわけではありませんので、加害者に対して強制執行をかけるなどして自分で回収しなければなりません。
一方、刑事法廷では、加害者の行為が「暴行罪(刑法第208条)」や「傷害罪(刑法第204条)」に該当するかが審理されます。賠償義務があるかといったお金の話は基本的に審理対象ではありません。なお、刑事で訴えられている人は「被告人」と言います(刑事事件で訴えているのは「国」です。)。
このように民事と刑事は全く別の手続であるため、判決の内容が異なることも稀にあります。たとえば、刑事では無罪だったのに民事では不法行為と認められたということもありますし、逆もあります(少ないですが)。
ただ、いくつか刑事と民事がクロスオーバーすることもあります。主要なものは「示談」と「賠償命令制度」です。
よく知られている「示談」ですが、これは、民事上の賠償責任を果たし、刑事の裁判官に「ちゃんと民事上の責任は果たしたから罪を軽くしてください。」と主張する目的で行われます。示談が成立すれば、原則として民事責任は無くなりますので、刑事責任・民事責任のいずれの問題も一回的に解決されますし、犯罪被害者も刑事裁判の後に民事裁判を起こすといった負担を負わなくても済みます。
弁護士というと兎角加害者の味方という印象が強いですが、犯罪被害者のためになる活動もしています。
もう1つの賠償命令制度はあまり知られていないかもしれません。
これは、刑事裁判に続けて民事上の賠償額等を審理する手続です。この制度が生まれるまでは、犯罪被害者は示談ができなかった場合には、刑事裁判が終わった後にその裁判の記録を取り寄せて、その記録を使ってあらためて民事訴訟を提起しなければならず、かなりの負担になっていました。
このように、刑事で被害者となっても、今はある程度法的保護が図られていますが、「加害者の資力」という問題はほとんど解決されていません。すなわち、上述した示談はそもそも加害者にお金がなければできませんし、賠償命令でいくら「払え」という命令が出されても加害者にお金がなければ回収しようがありません。
一応、犯罪被害給付制度というものもあるのですが、故意による犯罪で重傷病を負った人しか使えませんし、法的賠償に比べると支給される金額は少ないです。
前述の「酔っぱらいに殴られた」くらいの事案では、加害者に前科前歴がなければ刑事の方は執行猶予判決となり、加害者に資力がなければ賠償金も得ることができず、いわゆる「泣き寝入り」になることも多いです。
そういった事態に陥らないためには、「君子危うきに近寄らず」で、危険そうな場所・人には近づかないことです。
犯罪被害に遭っても常に被害回復がなされるわけではない、ということをしっかりと認識しておきましょう。
いかがだったでしょうか。
余談ですが、「弁護士はなんで犯罪者を擁護するのか。」と思われている方は多いのではないでしょうか。私も、いつかは子どもに聞かれるのではないかと思っています(私個人は、今は刑事弁護士の仕事はほとんどしておりませんが。)。
昔は、弁護人という制度は存在せず、捜査する人、処分を決める人、は一緒でした。捜査や処分の適正を批判する立場の人がいないとどうなるかというと、どうしても捜査・処分は適当になります。誰からも批判されないから適当に犯人を決めてしまえ、罪の重さを決めてしまえ、というようになってしまうのです。歴史的に、このような制度的瑕疵によって、罰せられるべきではない人たちが罰せられ、また行為に対して重すぎる処分を科せられてきました。
そうした歴史的経緯もあり、現在の先進国の多くは、罪があった・重く処罰すべきだと主張立証する者(検察官)、罪がなかった・軽く処罰すべきだと主張立証する者(弁護人)、これらの者の意見と証拠を中立的な立場から見て処分を決める者(裁判官)を分けています。
「弁護士はなんで犯罪者を擁護するのか。」に対する答えは、「そうしないと不適切な処分がなされる可能性が高くなるから。」ということになるのですね。
以上