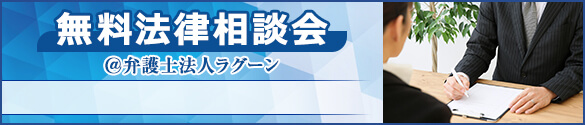第80回メルマガ記事「立法事実と法律の解釈適用」
弁護士の内田です。
9月は連休が多いですね。従業員にとっては嬉しい限りですが、経営者にとってはその分売上がないということなので不安になります。とはいえ、休日にしっかりとリフレッシュして休まないと良い仕事はできないと思っていますので、休日はあまり仕事のことは考えずに過ごしています。
まだ弁護士になったばかりの頃は、寝ても覚めても仕事のことばかりを考えて、休日も十分に休めない(と分かっているので休日出勤して仕事をする)ことも多かったように思います。
経験を重ねてくると、仕事の精度・速度も上がったのか、あまりそういったことは無くなりましたが、それでもたまには「あの件の判決は怖いなぁ。」とか気にしても変わらないようなことを考えて込んでしまうことがあります。
「今は人事を尽くして天命を待っている状態だ!」と堂々と出来ればよいのですが、「やっぱり、あのときはああしておけば良かったかも」などと過去を悔いるのが人間です。そんなとき、皆さんはどのようにして精神のリカバリーを図っておられるでしょうか。
私は、変に気にしないようにするのではなく、自然と心が「もう、考えてもしょうがない。」ってなるまで悩みに悩みぬきます。考えたことをスマートフォンのメモ帳に書き殴ったりします。言葉にすることによって、実はそんなに悩むような話でもない(若しくは、まだ悩む段階ではない)ことに気付かされることがあります。不安・悩みを文章にしてみるというのはメンタルコントロールの1つのポイントなのではないかなと思います。
さて、本日のテーマは「立法事実と判例変更」です。
立法事実というと難しいように聞こえますが、要は、法律が作られるに至った際に前提としていた社会的な事実(その当時の世間一般の価値観といったもの含まれると言ってよいでしょう。)のことを言います。
法律が出来るのにはそれなり理由があります。たとえば、借地借家法という法律は土地建物の借主を民法よりも手厚く保護しています。この法律が制定された当時、借主の立場が弱く「借家を追い出されて生活に困る人が多くいた。」「建物の取り壊しが頻発していた。」といった事実があったわけです。これが立法事実となって、「じゃあ、借主をもっと保護しよう。」ということになって法律が出来たわけです(厳密には、前身として借家法・借地法という法律がありました。)。
最近だと結婚後の男女別姓なんかも議論されているところです。これは憲法第14条の平等の問題でもありますが、「結婚したら女性は男性の姓を名乗る。」という条項が制定された当時にはそれが当然という社会の価値観があったのかもしれないが今はもう違うのではないか、つまり「今はもう立法事実がないのではないか。」という議論だとも捉えることができます。
立法事実が無くなって国民サイドから不要論が出てくれば国会においてその法律が廃止され、また行政レベルでその法律の執行がなされなくなることもある一方、立法事実が無くなり、また無くならないまでも相当変化したにもかかわらず、変わらず適用され続けている法律もあります。
立法当時には存在していた事実が変化した場合、法律自体が変わることもありますが、法律の「解釈」が変わることもあります。最高裁判所が「ここでいうAというのはBという意味と解する。」と過去に判断を下していたものを「ここでいうAというのはCという意味と解する。」と変更することを判例変更と言いますが、こういった判例変更の背景には、立法事実の変化があります。
有名な例は、強制わいせつ罪の解釈変更です。最高裁は、昭和45年時点では、強制わいせつ罪の成立には加害者に「性的意図」が必要との判断をしていましたが、平成29年の判決では不要であるとして判断を変えています。
判旨で述べられた理由は、被害者の受けた性的被害の有無・内容にこそ目を向けるべきであって加害者の性的意図を犯罪の成立要件とする解釈の根拠を見出すことは難しくなっている、というものでした。これは、昭和45年から平成29年にかけて社会の性犯罪に対する批判が厳しくなり、昭和45年とは法解釈を行う上での前提事実が大きく変わっているために解釈を変更したものと言い換えることができます。
このように、立法にしても法解釈にしても永遠不変のものではなく、時代が変わり、立法当時又は解釈当時に前提とされていた事実が大きく変化した場合には時代に合わせて変化します。
さらに下位のレベルでは、事実認定のレベルにも影響があります。企業法務において重要な論点は、解雇権濫用法理規定(労働契約法第16条)の運用です。
この条項は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めるものです。ここでいう「合理的」とか「相当」という要件は極めて抽象的な文言で、結局のところ、裁判官の事実認定にかかっています。
この条文は会社にかなり厳しく運用されることも多く、一般のビジネスパーソンからすると「そんなことをしてもクビにならないの?」「そんな迷惑な人を辞めさせられないの?」と思うような判決が出されることも少なくありません。
労働契約法自体は平成19年(2007年)に公布された法律ですが、第16条の基になった判例は昭和50年(1975年)に出されています。そこで、これらの判例・法律が生まれたときの背景に着目してみると、昭和50年の有効求人倍率は0.6倍、平成19年は1.02倍でした。
リーマンショックなどもあり、我が国の求人倍率が安定して1を超え出したのは平成26年(2014年)当たりからです。
解雇権濫用法理の判例が生まれたときはいわゆる「買い手市場」であり、一旦職を失った人は再就職が厳しいでした。また、その状況は、立法時もそう大きく変わっていなかったといえます(昭和50年に比べると平成19年はかなり良かったとは思いますが・・・)。つまり、解雇された労働者を法により保護する必要性が高かったのです。
では、今は、と言いますと・・・お察しのとおり新型コロナウイルス蔓延の影響で有効求人倍率は低くなっています。ですが、2021年で1.16倍、コロナ前の2019年は1.55倍、2018年は1.62倍です。
我が国の労働人口の少子高齢化を踏まえると、現在は一時的に労働力需要が低下しているだけで、アフターコロナ後はまた1.5倍前後に戻るのではないかと推測されます。
このように、解雇権濫用法理が生まれた当時と現在とでは労働市場環境は大きく変化しています。しかし、以前として昭和50年にいるのではないかと思うような判決を見かけます。「昭和50年の判決は会社に厳しい事実認定をしている。だから、裁判所は今も会社に厳しめに事実認定すればよいのだ。」という思考回路になっているのかもしれません。
他方で、地裁・高裁と会社に厳しい判決が続き、最高裁が労働者に厳しい判決を下す、という例も最近では現れています。
最高裁は、時代が変わってきていることの警鐘を鳴らそうとしているのかもしれません。事実認定レベルで最高裁があえて控訴審判決を覆すことは珍しいからです。
いかがだったでしょうか。
法律の解釈・運用がコロコロ変わるのは問題ですが、先例至上主義で時代の変化を無視した解釈・運用がなされるのも困ります。
法律(立法)にしても、法律解釈適用(司法)にしても、大きな影響を及ぼすのは我々国民の「声」ですから、我が国の世論は、もうちょっと立法とか司法に対する意見を発信すればよいのに、と少しだけ思います。