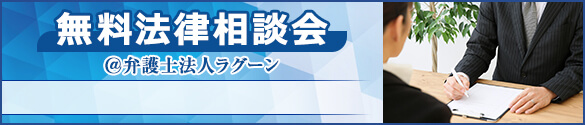第100回 降格に関する最近の裁判例
弁護士の内田です。
多くの会社では、今頃が夏季賞与の季節ですね。貰える労働者にとっては嬉しい季節ですが、支払う使用者にとっては頭を抱える季節です。
会社の規模や目的によって賞与の決め方はマチマチだと思いますが、当法人では支給時点での予想利益額から賞与原資を決定し、その原資を評価点数(労働者自身が付けた自己評価をベースとした上司の評価)で按分するという方法を採用しています。
このような方法を採用している企業は多いのではないでしょうか。
賞与と同時に、使用者の頭を悩ますのが「昇進」「降格」です。賞与の評価基準もそうですが、どういう行動、どういう結果をプラスに評価するのかは、その会社の骨格を表すものです。「会社としては、労働者の皆さんにこういう行動を取って欲しい、こういう結果を出して欲しい、と思っています。」という強力なメッセージになります。
中には賞与の支給基準や昇進降格の基準をオープンにしていない企業も見受けられますが、勿体ないことだと思います。
さて、本日のテーマは冒頭の話と関連して「降格に関する最近の裁判例」です。昇進に対して文句を言う人はいないので、必然、争われて裁判例になるのは降格です。
まず、法律的には一口に降格と言っても2種類あるので、これを抑えておかなければなりません。
1つは「人事権の行使としての降格」であり、もう1つは「懲戒処分としての降格」です。今回のメルマガで取り扱うのは前者です。
後者の方は、「裁判所の審査はかなり厳しい」とだけ理解しておいてください。
本日、ご紹介するのは東京高裁で令和4年1月27日になされた判決です。
まず、規範(法律的な判断の枠組み)としては、骨子として「職位の引き下げとしての降格は就業規則等に規定がなくても人事権の行使として行うことが可能であり、使用者には広範な裁量が認められるが、業務上の必要性の有無、程度、労働者の能力、適性、労働者の受ける不利益等の事情を考慮して、人事権の濫用があるといえる場合には無効になる」と判示しました。この考え方自体は新しいものではなく、かなり昔から判例・裁判例として確立していた考え方です。
ただ、降格に伴う賃金の減額については就業規則等に明確な根拠が必要とする裁判例が多いので、企業としては賃金規程等に降格と共に賃金が減額されることを明記しておくべきですし、役職・等級の低下によりいくらの賃金減額になるのかが分かるように明確に規定しておくのが無難です。
上記事案では、被告は人事のシステム構築サービス、システム運用管理サービスなどを提供する会社で、原告は被告においてサービスプロデューサーとして勤務する労働者でした(職責給約53万、役職給7万円)。
被告は、平成28年1月に原告をチーフプロジェクトマネージャーに降格し、これに伴い役職給は7万円から3万5000円に減額しました(以下、「第一降格」と言います。)。さらに、被告は平成28年2月に、さらに原告を役職なしに降格しました。これに伴い役職給は0円となりました(以下、「第二降格」と言います。)。
裁判所は、第一降格については原告についてマイナスの評価がなされていたということを認めるに足りる証拠がなく(逆に原告所属の事業部の目標利益達成率が93%であったことや受注も数件あったことを認定しています。)、原告が受ける不利益も小さいとはいえないことを理由として無効と判断しました。また、第二降格についても、1カ月足らずでチーフプロジェクトマネージャーとしての役割を果たせていないと判断するのは短すぎるとして無効と判断しました。
この判決の評価ですが、皆さんも第二降格が無効になるのは予想が出来たと思います。一方、第一降格については会社に厳しい判断でした。
裁判所が「会社には広範な裁量が認められる。」と言っているのだから基本的に会社が勝つと考えてしまいますが、裁判所が言うこのような規範は言葉遊びみたいなところがあり、結局のところ、担当裁判官のさじ加減です。たとえば、会社にほとんど裁量がないと考えられている解雇についても、裁判官が「権利の濫用だ。」と思えば無効です。
結局のところ、最後は裁判官の価値判断であること、そして裁判官の価値判断は必ずしも全て判決文に書かれるわけではないということが重要です。
裁判官が会社を勝たせるためには判決書に「論理的に見て会社を勝たせた。」と言えるだけの理由が必要です。会社は、降格させた労働者の能力不足・目標不達の具体的内容、それによって生じた会社の業務に対する影響、会社は十分な指導をしてきたが労働者が改まらなかったことなどを主張立証できるように平素から証拠確保の措置を講じておかなければなりません。しかし、それだけでは不十分であり、裁判官に「この事案は会社を勝たせるのが公平にかなう。」と思ってもらえるような背景的な事情も(必ずしも判決書に引用されなくても)過不足なく主張立証する必要があります。
人事権に基づく降格であっても、争われることを前提とすれば記録化の作業量は膨大になります。最終的には、経営判断として、降格が争われる可能性や争われて負けた場合のリスクの程度と訴訟で手堅く勝つために証拠化にかかるコストを比較衡量して、どこまで証拠化に取り組むか決めることになります。
いかがだったでしょうか。
裁判官は、兼業や商売をすることが原則として禁じられています(裁判所法第52条)。ほとんどの人は労働者のみ経験して裁判官になるため、経営側の事情というものを十分に理解した裁判官は少ないです。司法改革により現在は様々なバックグラウンドを持った人たちが法曹になっていますが、経営者から裁判官という人はまだまだ少ないと感じています。
将来的には、そういった裁判官が増えることを祈っています。