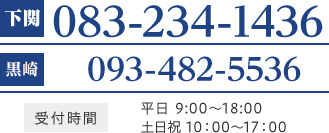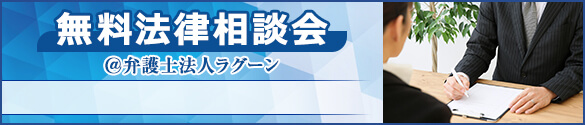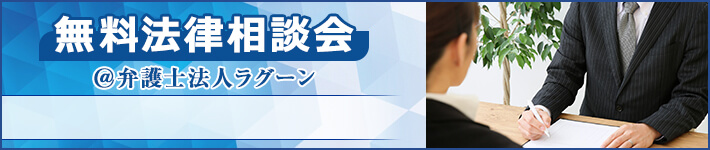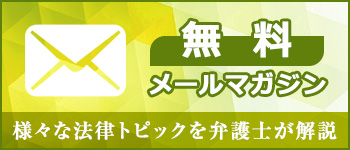第116回 1票の格差
弁護士の内田です。
今年はとても暑いですね。日差しは、暑いというよりも、もはや痛いです。
テーマパークなどは、酷暑から来客者数が減少しているようで、日本経済全体にも打撃になっているようです。アイスクリームも暑すぎると逆に売り上げが減るそうです。
今後は、「涼」ビジネスが拡大していくのではないでしょうか。調べたわけではないですが、漫画喫茶など涼しい環境でのんびり過ごせる系のビジネスの売上は増えるのではないか(増えているのではないか)と思っています。
ピンチはチャンスの精神で、経済的にもこの酷暑を乗り切っていただきたいものです。
さて、今回のテーマは、「1票の格差」です。
選挙の時期には、いつもニュースになっていますよね。なぜ1票の格差の問題が毎回ニュースで流れるのか不思議に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこには、企業経営でも参考になる考え方があります。
日本国憲法において、裁判所が特に重視している権利・自由が「選挙権」と「表現の自由」です。逆に、軽視していると言ってよいのが営業の自由など経済的自由です。
これはなぜかと言いますと、たとえば、特定の企業や団体だけを優遇して国民の営業を制限するけしからん法律が出来たとします。でも、国民が「表現の自由」に基づいて特定の政党や法律を批判することができるのであれば、国民同士で議論し「あの法律は撤廃すべし」という民意を形成することができます。そして、国民は、その法律を撤廃すると宣言する政党・立候補者を「選挙権」に基づいて選ぶことで、その法律を撤廃することができます。
このように、「表現の自由」と「選挙権」さえ守られていれば、けしからん経済規制の法律が出来たとしても国民自身の力で変えることができるというように考えているのです。
1票の重みに格差があると、当たり前ですが、100人の国民中70人がA法律に反対していたとしても、A法律を支持する政党・候補者が選ばれるということが起きます。民意が政治に正確に反映されないのです。
これは、立憲民主主義的には大問題です。
このような理由から、1票の格差問題は必ずといってよいほどニュースになります。
とはいえ、制度的に格差を0にするのは難しいでしょう。諸説ありますが、2倍以上の差は生じないようにすべきというのが多数説です。1人が2人以上のパワー(選挙権)を持つのは容認できないという考え方です。
企業経営においてあまり選挙ということはないでしょうが、「表現の自由が確保されていれば不適切なルールは自浄作用で変えることができる。」という考え方は企業経営においても大切です。このような思想は、内部通報制度などにも表れています。
「おかしいんじゃないか」と言える環境と、それがルールの制定者(会社だと経営陣)の意思決定に影響を与えうること、そういった仕組が企業にも必要です。
いかがだったでしょうか。
人は善か悪かといった話もありますが、制度によって人は善にもなり悪にもなるのではないかと思います。
経営者として、良い制度作りをしていきたいものです。