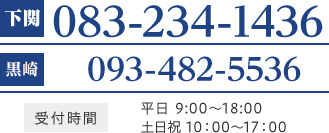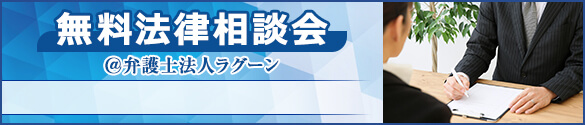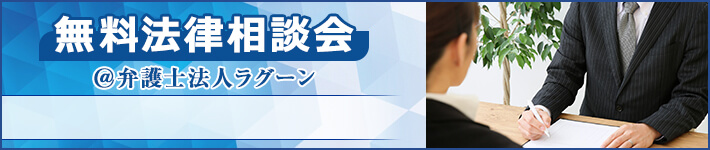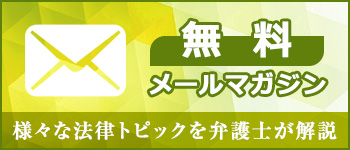第119回 パワーハラスメントの認定に関する最新裁判例のご紹介
弁護士の内田です。
やっと暑い日が去ってくれましたね。
最近、春と秋がどんどん無くなってきている気がします。暑いか、寒いか、です。
春秋は、エアコンも必要ないのでお財布にも優しいのですが、夏冬は逆です。物価高と叫ばれている昨今ですが、夏冬の長期化によっても国民生活は圧迫されてきているのかもしれませんね。
さて、本日のテーマは、「パワーハラスメントの認定に関する最新裁判例のご紹介」です。長いので、以下「パワハラ」と言います。
本日、ご紹介したい裁判例は、東京地裁令和5年12月7日判決です。
この判決の特筆すべき点は、そのパワハラ認定の手法にあります。
事案の要点としては、原告(パワハラ被害者)が自席で業務に関連する本を読んでいたところ、上司(パワハラ加害者)が原告に対して、「業務中に仕事と関係しない本を読むのは就業規則違反だ。」と注意し、原告から「業務に関連する本を読んでいた」という反論があったものの、虚偽と断じて罰則の適用がありうると警告したというものです。
これについて、裁判所は、上司や被告(会社)は、原告の主張に関して容易な事実調査すらせずに虚偽と断じて罰則の適用を警告していることが、パワハラに該当すると認定しています。
パワハラというと、言った内容がどうとか、叱ったときの状況や長さばかり問題となるイメージだったかもしれません。しかし、本件は、事実確認の有無もパワハラ認定に大きく影響することを明示しました。
争いのある事実は、ちゃんと調査をして、確定する、ということは司法界においては当然の考え方なのですが、それをしていないことが「パワハラ」の評価に結びつくというのは少し目新しい考え方のように感じました。
ところで、本件の原告は、上司に「ブス」と言ったり、副社長・社長・その他上司ら宛てに「特定の上司から指示されていることに従うと会社に損失を生じる危険があるが、それでもその上司の指示に応じるべきか」とメールするなど、問題行動が目立つ人でした。
そういうこともあって、被告代表者は原告に対して退職勧奨を2度行っているのですが、これもパワハラと認定されています。その際にも、「原告の言い分を十分に聴取することなく事実確認や背景事情の確認が不十分であったこと(不十分なのに退職勧奨を行ったこと)」がパワハラ認定の理由とされています。
きちんとした事実調査・認定を経ないで圧力をかける行為は、広くパワハラと認定される可能性があるということですので、事実確認は怠らないように注意しましょう。
いかがだったでしょうか。
ハラスメントの概念は曖昧で人によって考え方が大きく異なります。
曖昧な概念は、歴史上、力を持つ者によって濫用されてきました。
曖昧な概念とそれに基づく罰の下では、人は萎縮的になり、適用者の顔色ばかりを伺うことになります。愚かな歴史を繰り返さないためにも、裁判所には、ハラスメント概念の明確化に取り組んでもらいたいものです。