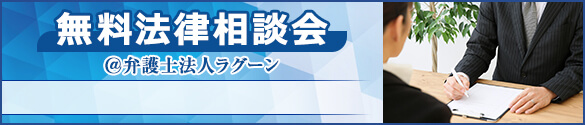第59回メルマガ記事「曖昧の活用」2020.12.25
「曖昧」の活用
弁護士の内田です。
もう年末ですね。年々、1年が過ぎ去るのを早く感じるようになってきている気がします。
まだ今年を振り返って・・・という心境にはなく、まだいかにあと数日で仕事を片付けられるかというモードですが、事務所の大掃除を終えた後には少しゆっくりと今年1年を振り返ってみたいと思います。
今年も色々な事件があったのですが、毎年色々な事件があるので、何となく毎年同じような雑感になってしまっています。
来年は、曖昧な言い方ではありますが、事件処理や事務所経営以外のことについても目標を立てて達成を目指していきたいと考えています。
さて、本日のテーマは、法律的な観点からみた「曖昧」の活用です。
日常的な言葉でもよく使う「曖昧」ですが、実は、法律的にはとても重要な概念です。
法律は、「曖昧」を嫌います。法律は国民の守るべきルールであり、その内容は明確でなければならないからです。「二義を許さず。」と言うこともあります。つまり、誰がどう読んでも1つの意味にしか読めないようにしなければならないということです(一義的、という言い方をします。)。
特に曖昧を排除しなければならないのは、刑法などの刑事罰を定める法律の条項です。たとえば、「悪いことをしたときは、10年以下の懲役に処する。」というような曖昧な条項があったとした場合、国民は何が「悪いこと」に該当するのか判断できず、怖くて常に萎縮して生活しなければならなくなります。
また、権力者が曖昧な文言を恣意的に解釈して国民を苦しめてきたという歴史もあります(我が国においては過去にあった「治安維持法」などが有名ですね。)。
これらの理由から刑事系の条項は概ね一義的になっています。
一方で、民事系・行政系の条項は、かなり曖昧なものが多いです。企業の関わる「ザ・曖昧条項」といえば労働契約法の解雇の条項でしょう。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この条項でいうところの「合理的な理由」「相当」という要件を充たさない場合には解雇は無効となり、その結果、会社は解雇した日から遡って賃金を支払わなければならなくなります。
この条項だけ見てもどういう場合が「合理的な理由」があるといえ、「相当」といえるのかさっぱり分からず、会社は解雇を躊躇してしまいます。
実際には、多数の裁判例を分析するとある程度「こういう場合は適法になり、こういう場合は違法になる」というのが分かるのですが、それでも裁判所がどのような判断を下すのか100%の予測ができないため、弁護士ですら解雇は最後の手段としてあまり推奨しません。
以上のとおり、曖昧な条項とリスクが合わさると、人は萎縮的になります。ですので、原則として法律は曖昧さを排除しようとします。
ただ、この「曖昧さ」は契約実務において良くも悪くも活用されています。
A社がB社に商品Xの製造を委託し、製造された商品Xを一定数A社がB社から買い取るという契約を例にお話しします。なお、B社は商品Xを製造するために一定の設備投資をしなければならないとします。
このような契約では、A社としては商品Xの市場動向に鑑みて柔軟にB社との契約を終了させたいと考えます。極端にいえば、商品Xを売り出して数カ月売れ行きが良くなければ直ちに契約を切りたいというわけです。
他方、B社としては、設備投資をしている以上、簡単に契約を切られても困ります。少なくとも、設備投資分が回収できる期間以上は契約を続けて欲しいというわけです。
A社としては、契約期間中であっても柔軟に契約を解約できるように、契約の中途解約事由はいかようにも読める曖昧な文言にします。たとえば、「市場において商品Xの需要が乏しいことが判明したとき」などです。
A社としてはB社に製造させてみて売れなかったらすぐにこの「需要が乏しいことが判明した」にあたるとして契約を解約するわけです。
逆にB社としてはA社の都合で簡単に解約されても困るので、上記のような曖昧な中途解約条項は削除を求めることになります。最低でも、「商品Xの販売個数が3カ月連続して〇〇個以下となったとき」というように明確化するよう求めます。
このように、契約実務において曖昧さは有利にもなりえますし不利にもなりえます。ですので、契約書の中で曖昧な条項を見つけても直ちに明確化を検討するのではなく、まずその曖昧さが自社に有利になるのか不利になるのかを見極めなければなりません。
いかがだったでしょうか。
来年にはワクチンにより新型コロナウイルスの影響が収まって、世界がまた活性化することを祈っています。
苦しいときが続きますが、皆様と共に頑張っていければと思います。