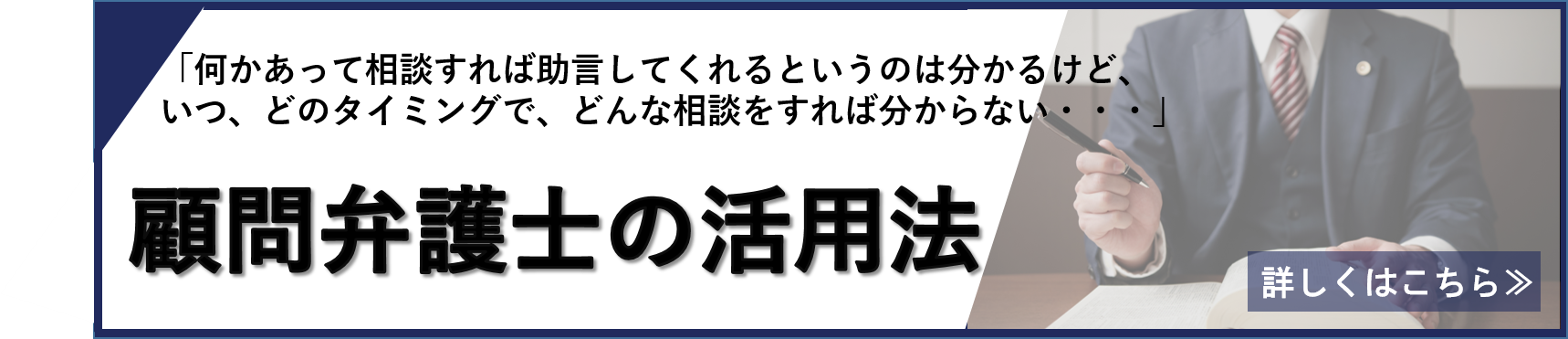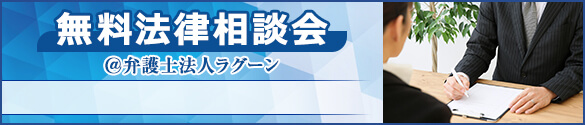賃金と就業規則
1 賃金と就業規則の関係
労働者の賃金は契約によって決まります。雇用契約書に「基本給月〇〇万円」「〇〇手当月〇万円」と記載されていることもありますが、細かい手当等は賃金規程に記載されていることが多いです(なお、勘違いされている方も多いですが、「就業規則」というと就業規則の附属規程である賃金規程なども含まれます。以下でも特に断らない限り、就業規則といった場合には賃金規程、賞与規程、退職金規程などの附属規程を含みます。)。
雇用契約書に「本書に定めのないところについては就業規則の定めによる。」と記載されていることが一般的ですが、この場合、会社と労働者の間では、「賃金は賃金規程の定めに従う。」という合意がなされたことになります。つまり、賃金規程が契約書の代わりになるのです。
そして、一旦、契約が成立した以上、どちらか一方が勝手に契約の内容を変更することはできません。このことを端的に示しているのが労働契約法の以下の条文です。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を
変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、
かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である
労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の
変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
合意があれば契約内容を変更できるのは当然で(第8条)、逆に、合意なく契約内容を変更することはできないのが原則ということになっています(第9条)。就業規則を変更することで労働条件を会社が一方的に変更できると誤解されている方も多いので注意が必要です。
この原則に対する例外を定めたのが第10条で、就業規則の変更に合理性がある場合には労働条件も変更後の就業規則にしたがって変更されます。これを賃金について当てはめると、「原則として賃金規程を変更することで賃金を減額することはできないが、当該減額変更について合理性がある場合には減額変更は有効になる」ということになります。
2 賃金規程の変更が無効とされた場合のリスク
たとえば、従業員の基本給を1万円減額する旨の賃金規程の変更を行い、当該変更の日から2年が経過したところで訴訟において無効との判断が下されたとします。この場合、当該訴訟の原告には1万円×24カ月(2年)=24万円+遅延損害金等を支払わなければならなくなります。また、理論的には、従業員が100名いれば、24万円×100名=2400万円+遅延損害金等の支出になります。
また、みなし残業代(実際の残業の有無にかかわらず一定の残業代(正確には「割増賃金」と言います。)を支払う制度)など残業の対価であることの明確性が求められるような性質の賃金の場合、賃金規程等がないと当該賃金の性質の証明ができず、結果として残業代の二重払いを強いられることになります。
このような予想外のキャッシュアウトを生じてしまうと資金繰りに致命的な支障を生じる危険性もありますので、賃金規程の変更が後で無効と判断されないように法的に妥当な手続を踏むようにしなければなりません。
3 賃金変更時の注意点
前述のとおり、会社が賃金規程を変更することにより一方的に賃金を減額することはできません。固定給を一部減額して歩合給を導入するといった変更もそれが労働者に不利益である限り同じです。
労働契約法第10条の定める要件は満たせば一方的な変更は可能ですが、条文を見ていただければ分かるとおり、その内容は極めて抽象的で、判例・裁判例の蓄積はあるものの(この判例・裁判例を集めただけで1冊の分厚い本になります。)、最終的に訴訟で不利益変更の合理性が争われた場合に、担当の裁判官が「合理性あり」「有効」と判断してくれるかどうかの予測は極めて難しいのが実際のところです。
したがいまして、基本的には、賃金規程を労働者に不利益に変更して労働条件を変更しようとする場合には、第10条によるのではなく、第8条によるべきということになります。つまり、労働者から「変更後の就業規則のとおり労働条件が変更されることに同意します。」という同意書を取り付け、「合意」によって労働条件を変更するのです。
ただ、同意書さえ取り付ければよいというものではありません。裁判所は、労働者が会社に比べて弱い立場にある考慮して、労働者の同意について「自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すること」を求めるなど、労働者の同意の存在について厳しく認定する傾向にあるからです。
そのため、会社としては、あとで「有無をいわさず署名押印させられた。」など言われて敗訴しないように、就業規則の変更の必要性について説明を行ったことを証拠として残す、同意書に賃金・労働時間など労働条件の重要部分について変更後の内容を明記するなどの対策も講じておく必要があります。
最後に、就業規則の変更時期ですが、「平時」に行うべきです。
労使間紛争が発生し、会社と労働者の関係が劣悪になった場合(有事の際)には、労働者が不利益変更に同意することはありません。業績がそれほど悪くなく、労使の仲も円満なときにこそ就業規則を見直し、将来に向けて変更を行うべきなのです。