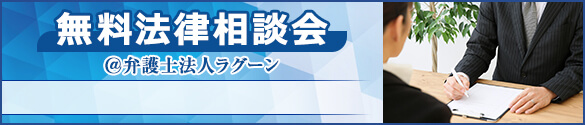第87回「メンタルヘルスと企業の対応」
弁護士の内田です。
最近、強盗事件が増えていますね。しかも、犯行メンバーは知らない人同士でインターネットを介して組織されているということで、物騒な世の中になったものです。
法律家の常識ですが、窃盗と強盗の間には大きな差があり、強盗は非常に重罪です。法定刑でいえば、窃盗は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、強盗は5年以上の有期懲役です。
窃盗は初犯であれば不起訴になることも多く、起訴されても執行猶予が付くことがほとんどです(実刑になる場合も大体1年以下です。)。これに対し、強盗の場合は証拠不十分でない限りほぼ間違いなく起訴され、執行猶予も基本的に付きません。つまり、初犯であっても即実刑かつ最低でも5年以上(例外はあります)ということになるのです。こうなれば、人生の立て直しはかなり難しいでしょう。
上述した強盗事件には「指示役」がいるようで、若者がハイリスクな実行役を担当しているようです。若者の人生や被害者のことを何とも思わない指示役の恐ろしさもさることながら、私は金欲しさに知り合いでもない人たちと強盗を実行しようとする若者の軽率さにも恐怖を感じます。
TV報道を見ていると、その若者たちは指示役から住所や家族を知られて後で脅されていたりするようですが、そうなることや刑務所送りになることを想像しないのでしょうか。
この手の犯罪が減少することを祈るばかりです。
さて、今月のテーマは、「メンタルヘルスと企業の対応」です。
昨今、「うつ病(うつ状態)になった。」と主張する労働者が増えているところです。会社としては、労働者から医師の診断書を交付され「明日から休業します。」と言われた場合、どのように対応したらよいのか苦慮するものです。
このような労働者への対応を誤った場合、会社に生じる不利益は様々なものがあります。
たとえば、裁判例・判例において労働者から診断書の提出があったにもかかわらず会社が休職させるなどの措置を採らず労働者が自殺してしまった事案では会社(及び上司個人)に約1700万円の損害賠償が認められていますし(労働者側の過失・素因の影響度が高かったとして8割の減額がなされてこの金額になっています。東京高裁平成14年7月23日判決)、あり得ない被害妄想を述べている労働者を就労不可能と判断して解雇した事案では解雇が無効と判断され、会社にはバックペイとして1500万円以上の支払い(バックペイ)が命じられています(最高裁平成24年4月27日判決)。
このような事態を回避するために、うつ病等の精神疾患を主張する労働者、又は外形的に精神疾患への罹患が強く疑われる労働者への対応を学んでおく必要があります。
まず、大原則として「素人判断はしない。」ということが挙げられます。医師の「うつ病である。〇カ月の療養が必要である。」という診断書があるにもかかわらず、会社が素人判断で「彼(彼女)は昨日まで普通に笑ったりしていた。そんなはずはない。」などと素人判断でうつ病ではないと決めつけ、出勤を強要するなどして万が一のことがあれば、ほぼ100%会社が責任を負うことになります。
会社の基本スタンスは、「こちらも医師に対応を確認する。」です。医師VS素人という構図にならないように、会社も医師(産業医等、会社の実情をよく知っている医師が望ましいです。)に相談し、そのアドヴァイスに従いましょう。勿論、この医師とのやりとりは証拠として記録に残しておく必要があります。
なお、診断書を書いた主治医から聞き取りをする際には、個人情報の関係で労働者本人から診療情報開示の同意を取り付ける必要があります。
主治医にとって患者は顧客である面は否定できませんし、基本的には患者の言葉だけを基にして診断をするため、中には患者の言うままに精神疾患の診断書を書く医師もいます。そのため、実務上、首をかしげたくなるような診断がなされることがありますが、「素人判断」が医師の判断に勝ることはないのです。
以上の大原則を前提に、2つのパターンについて解説していきます。①明らかな被害妄想が認められるなど精神疾患への罹患が強く疑われるにもかかわらず本人がそれを認めない場合(=まだ医師の診断がないケース)、②既に診断書が提出されており精神疾患を理由に欠勤又は休職している場合(≒医師の診断があるケース)の2つです。
まず、①ですが、上述した大原則に従い「素人判断」はせず、会社は労働者に対して産業医等の医師の診察を受けることを勧めます。
なお、診察を拒否する者に対して受診命令の発出を検討する場合もありますが、頑なに診察を受けない者に対して受診を強制することは事実上不可能ですし、受診命令違反を根拠に懲戒処分をするのもリスクがあるため、あまり実行されることはありません。
即解雇も基本的に避けるべきです。上記判例において、精神不調により欠勤していると認められる労働者に対しては、まず治療を勧めて休職等の処分を検討してその後の経過を見るなどの対応を採るべきだと判示されているからです。このような措置を採ることなく即解雇した場合、その解雇は無効となります。
では、医師の診断を一切受けない者に対してはどうするべきなのかということですが、休職制度を使います。ほとんどの会社では休職制度が用意されているかと思いますが、ここでの注意は私傷病休業しないことです。「病」と認定することはできないからです。就業規則の定め方によりますが、精神疾患への罹患が「疑われる場合」や「その他前各号に準じる事由がある場合」といった条項を適用します。
休職命令の発出要件は、基本的に債務の本旨に従った労務の提供できない、すなわち雇用契約上想定されている通常の業務が満足できない状態であることなので、実際に業務に支障が生じていることの証拠は確保した上で発出する必要があります(当該労働者のミスの記録や他の従業員からの聞き取り書面など)。
なお、出来れば命令といった一方的な方法ではなく、労働者に休職を促し、労働者の方から休職していただいた方が後で争われるリスクは低くなります。
休職命令に従わずに出勤を強行してきた場合にはどうすべきでしょうか。
前提として、法律上、会社は労働者の労務を受領する義務を負いません(労務の受領拒否によって賃金がどうなるのかは別問題です。)。また、自らの事務所・店舗につき施設管理権を有します。
したがって、会社は会社管理の建物への進入を拒否することができますので(管理者の意思に反して侵入した場合には「建造物侵入罪」という犯罪になります。)、会社管理の建物に入ることを禁止する旨の通知を出し、それでも入ってきた場合には警察に通報することになります。
次に、②ですが、ポイントは休職期間満了時の対応になります(①のケースでも休職に入った後の復職の際に問題となります。)。
まず、原則の確認ですが、復職を認めるかどうかの基準も債務の本旨に従った労務の提供ができるか否か、すなわち休職前の職務が問題なく遂行できるか否かになります。休職前と同様に働けないのであれば、原則として復職は認められないということになるのですが、この点、例外となる判例があります。
それが片山組事件判決(最高裁平成10年4月9日判決)であり、同判決によれば、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」とされています。簡単に言ってしまえば、原職の他に出来そうな仕事があって、労働者がその仕事に就きたいと言っているのであれば、復職を拒否してはダメですよということです。
このような判例があるため、会社は復職の可否の判断に際しては、他部門での就労可能性についても検討しなければなりません。さらにいえば、復職を認めないという判断する場合には、その時点での会社の状況(当該労働者の能力等で配置できる他の部門がなかったこと)を資料としてまとめておく必要があります。
ここで法務担当者の方が気になるのが「賃金」でしょう。復職した労働者を原職ではない他の業務に就かせた場合、賃金は変更することができるのでしょうか。
この問題は、労働者の同意を得て変更する場合と、労働者の同意なく変更する場合に分けて考えなければなりません。当然、会社としてまず検討すべきは前者です。
同意によって労働条件を変更することができるのが原則ですが(労働契約法第8条)、これについても判例があり、賃金の減額など重要な労働条件の不利益変更の際には、「変更を受け入れる労働者の行為の有無だけでなく、その変更により労働者にもたらされる不利益の内容および程度、労働者の行為がされるに至った経緯およびその態様、その行為に先立つ労働者への情報提供または説明の内容等に照らして、その行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべき」とされていますので、労働者の自由意思が問題とされることがあります。
しかし、これについては原職の業務は遂行困難という労働者本人の申出によって他の業務で復職するという形になるため、労働条件が多少不利益に変更されていても「合理的な理由が客観的に存在する。」という判断になりやすいです。
むしろ、問題は後者の労働者の同意がない場合です。契約上の根拠なく一方的に労働条件を不利益に変更することはできず、このことは休職からの復職においても異なるところはありません。
したがって、原職以外の職務への復職の際に賃金を減額する場合には、契約上の根拠たる就業規則にその定めが必要です。端的には、「復職の際、原職以外の職務を復帰する場合には、賃金は当該職務によって定める。この場合・・・(詳細な定めが続く)・・・」といった定めが必要になるということです。
これは簡単なようで実は難しく、たとえば、部によって異なる基本給テーブルが用意されていない会社では、原職が営業部の者が総務部で復職したとして基本給を変更することができません。また、仮に部ごとに基本給テーブルが存在していたとしても、原職で営業部のA3等級だった者を総務部で復職させる場合に総務部のどの等級にするのかといった問題も生じます(これをどう処理するのかを定めた規定も必要になるということです。)。
実務的には、仮に詳細な復職に関する規定が整備されていたとしても、やはり労働者及び医師とよく話をして、「〇〇部で〇カ月間は1日〇時間の労働、賃金は月〇〇万円とし、満了時点において原職で通常通り働けそうだったら元の労働条件に戻す。」といった事案(労働者の症状や会社の規模・業種等)に則した案を提案して労働者の同意を得るのが無難です。
なお、復職方法を検討するに当たって通常は復職可能の記載がある診断書等の提出を求め、医師の見解を基礎に話を進めていくことになりますが、まれに医師の診断書の提出を拒否したり、医師からの意見聴取を拒否する労働者もいます。そのような場合には、復職の可否の判断ができないということで、自動退職又は解雇の措置を採ることになります。
復職の可否を判断するための医師への意見聴取等を労働者が正当な理由なく拒否した場合について解雇を有効と認めた裁判例もあるところですので(大阪地裁平成15年4月16日決定)、会社としては医師への意見聴取を積極的に行った方が良いでしょう。
いかがだったでしょうか。
これを読まれて「会社は療養機関じゃないのにそこまで・・・」と思われた方も多いでしょう。ただ、裁判所も「当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして」と判示しているとおり、中小企業に過大な負担までを強いているわけではありません(と信じたいと思う裁判例も少なくないですが・・・)。
精神疾患に罹患したことそれ自体は気の毒なことではありますが、他方で、その人員を抱え続けることによる他の従業員の負担・不公平感も無視できるものではありません。安易に休職・復帰の繰り返しを認めていては、他の従業員まで心身を故障してしまう結果になりかねません。
自動退職扱いや解雇には大きなリスクを伴いますが、会社はどこかで線引きをしなければなりません。「これ以上は我が社では抱えきれない。」というラインを予め考えておくことが必要なのです。
また、この線引きを経営層が明確にしておくことが、メンタルヘルス問題で総務人員がメンタルを病むことの防止にもつながります。