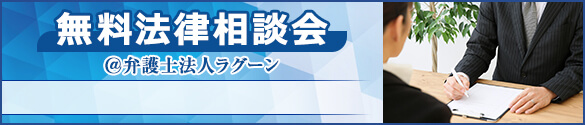第89回「代理権の認定について」
弁護士の内田です。
酷暑ですね。熱中症には気を付けなければならない季節です。
先日、法律事務所の経営者向けの会社視察ツアーに行ってきました。
某家具販売会社を視察したのですが、オフィスが綺麗でスタイリッシュでした。また、私の勝手なIT企業のイメージで従業員の服装が自由というのがあるのですが、その会社もそんな感じでした(髪の色なども自由な様子でした。)。
弁護士業は割と外見に気を使う(と私は勝手に思っている)ので、法律事務所であんまりカジュアルな格好を許容することはできないのですが、実のところ服装と業績にはあまり相関関係はないのかもしれません。
会長のお話の中で、「人に任せることが大切」という内容がありました。ビジネスではデリゲイション(delegation)と呼ばれて議論されている、いわゆる権限移譲というやつです。
おそらくですが、弁護士の多くは権限委譲が苦手です。大体、自分でやりたがります。私自身、意識的に任せてはいるのですが、「まだ彼・彼女にはこの仕事は無理だろう。」と思って自分でやってしまいがちです。
そんな私ですから、「会長はどのように基準・考え方で権限移譲をなされているのですか?」と質問しようと思ったのですが、ちょうど同じ質問を他の方がなされていました。
会長は、この質問に対し、「ポジションに見合った能力を得た者にポジションを与えるのでは遅い。ポジションを与えればそのポジションに見合った能力を身に着けるようになる。」とおっしゃっていました。とは言っても誰でもよいわけではなくて、やはり仕事に意欲的であるとか、他の従業員に好かれているとか、ある程度の基準はあるようでした。
どうして弁護士は権限委譲が下手なのかを考えてみると、結婚に消極的な評価をしている弁護士が多いのと同じ理由なのではないかという推論に達しました。すなわち、経営者は権限移譲して上手くいったとき、そのことをわざわざ弁護士に報告したりはしません。経営者が弁護士に報告するのは、大体の場合、「権限移譲したけど裏切られたとき」です。
弁護士は仕事柄「信じて任せたのに裏切られました!」という話ばかりを聞きますので、無意識に権限移譲に慎重になってしまっているのではないかと思うのです。
こういった思考の罠に囚われず、積極的に権限移譲を活用したいものです。
さて、本日のテーマは「代理権の認定」です。久しぶりに冒頭のお話とテーマが多少リンクしています。
実務上、そんなに数は多くのないのですが、契約した相手方から「うちはそんな契約はしていない。従業員が何の権限もないのに勝手にした契約だから無効だ。」といった主張がされることがあります。
まず、基本的な事項のおさらいになりますが、代表取締役がいる会社では、原則として、会社を代理する権限は代表取締役にしかありません。
皆様の会社で契約書に代表取締役の記名押印を行うのは、正に代表取締役にしか会社を代表する権限がないからです。
なお、ここで少し横道に逸れますが、たまに「この度、代表取締役が変わったのですが、契約書は作り直さなくてもよいのでしょうか。」という質問を受けます。
結論としては、作り直さなくてもよいです。契約締結時点で代表権(代理権)があった以上、契約は有効に成立しており、あとに代表者が変わったとしても契約の有効性が覆されることはないからです。
本筋に戻しますと、上述した理由で契約書には代表取締役の記名押印がなされるのが原則ですが、たまに大企業との契約書では「〇〇支店長」の記名押印しかない契約書も見受けます。
こういう場合、「代表取締役の記名押印にしてください。」と必ず言っておかなければならないのでしょうか。
私たちは、スーパーなどで買い物をしますよね。そのとき、「社長を出せ。」と毎回言わなければならないのかというと、当然そういうことではありません。現場の従業員には店舗の商品を販売する権限が代表取締役から与えられていますので、いちいち代表取締役が出張って来なくてもよいわけです。
会社 → 代表取締役 → (店長) → 現場従業員 という風に階層的に代理権の授与が行われているのです。
もうお分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、先ほどの例でも、代表取締役から〇〇支店長に当該契約について会社を代表する権限の付与(代理権の授与)が行われているのであれば、「〇〇支店長」の記名押印でも特に問題はありません。
問題となるのは、後で「〇〇支店長に今回の契約をする権限は与えていなかった。」と主張される場合です。契約の有効を主張する側に代理権の存在を主張立証する責任がありますので、このように争われると「〇〇支店長にはこの契約をする権限が与えられていたはずだ。なぜなら・・・」と主張して行かなければなりません。
それでは、代理権の存在を主張する側はどのような主張をすればよいのでしょうか。
裁判所は、このようなビジネスに関する代理権の存否について、①代理人の役職・職務、②当該契約の内容(会社にもたらす影響)、③契約締結までの本人の関与の有無・程度、などから認定を行っています。
たとえば、代理人(上記例では〇〇支店長)の役職が高位であるほど通常は幅広い権限が与えられているはずだということになりますし、職務の性質上必要不可欠な権限についても当然与えられていたであろうという推認が生じます(①)。契約の内容が会社にとって重大であればあるほど役職の低い者には権限が与えられなかっただろうという推認が働き(②)、契約締結までの交渉等について代表取締役が関与していた程度が高いほど権限授与があったと推認されます(③)。
このことを踏まえると、代理権を主張する側は、「〇〇支店長は従業員が500名もいる〇〇支店の支店長である。」「今回の契約の代金は〇〇万円であり、××社の年間売上でわずか△△%に過ぎない。」「契約書を取り交わした前日の商品確認の際に代表取締役も立ち会っていた。」といった事実を指摘し、「〇〇支店長には今回の契約を締結する権限が与えられていたはずだ。」と主張していくことになります。
一方、代理権を否定する側はこれと逆のような主張をすればよいということになります。
なお、代理権は委任状などの明確がないものがない限り、外からその存在を確認し難いため、「代理権があるだろう。」と信じて取引した者を保護する規定が多く存在します(民法109条、110条、112条など)。そのため、「相手に代理権が無くて大損害を被った!」という話はあまり聞きません。
数ある法務リスクの中ではそこまで神経質になる部類のリスクではないのですが、最近、私が代理権を否定する側で応訴した事案もありましたので、この度はご紹介させていただきました。
いかがだったでしょうか。
最近はTVでビックモーターの件が連日のように報道されていますね。
この件についても近いうちに何かの記事を書ければと考えています。
以上