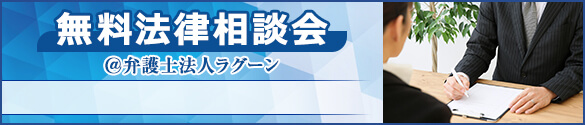第21回メルマガ記事「残業代請求に対する反論②」 2018.5.24号
弁護士の内田です。
本日は前回に引き続き、残業代(正確には割増賃金と言いますが、馴染みのある残業代という言葉を使います。)請求に対する会社の反論についてお話ししていきます。
その前に、ニュースで興味深い話がありましたのでご紹介します。
有名な企業であるカゴメですが、男女比率を50%にするために積極的に女性を採用するようにした結果、低迷していた業績が回復したというものです。
このように不利に取り扱われてきた人たちを特に優遇する措置を講じることをアファーマティブアクションと言います。カゴメの事例は、正にアファーマティブアクションの成功例といえるでしょう。
もちろん、単に女性の採用比率を多くしただけで業績が回復したのではなく、女性に配慮した職場環境の整備や男性社員の意識改革、業務改善などの経営努力の賜物なのだと思います。
当法人の事務局さんも女性が圧倒的に多いのですが、優秀な方が多く、非常に良く働いてくれています。人材難のこの時代ですから、会社は、高いポテンシャルを秘めているにもかかわらず労働市場に参加できていなかった女性を積極的に採用していく戦略を採った方が良いのかもしれませんね。
さて、本論に戻りまして、突然、従業員から「残業代を払え!!」と請求された場合、会社はどのような反論をすることができると考えられるでしょうか。
よくある反論としては、①残業してないじゃないか(主張している労働時間は誤っている)、②禁止していたのに勝手にした残業じゃないか(残業許可制に反している)、③あなたは管理監督者だから残業代は出ないよ、④うちは固定残業代制度を採っているから残業代は出ないよ、⑤もう時効だよ、というものが挙げられます。
ですので、これらを1つ1つを法律的な観点から見ていきましょう。
まず、①の「主張している労働時間は誤っている。」という反論ですが、たとえば、変形労働時間制を採用している場合にそれを従業員が知らないで残業代を請求してきた場合に使うことがあります。
変形労働時間制でよく見るのは1カ月単位の変形労働時間制ですが、これは、1月の一定期間内での所定労働時間を平均して法定労働時間を超えなければ、1日又は1週の法定労働時間を超えて労働しても残業代が発生しないという制度です。
たとえば、6月4日に10時間働いた場合、1日の法定労働時間である8時間を2時間超えているので通常なら残業代が発生するのですが、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用している場合、6月1日とそれ以外の6月の日の所定労働時間を平均して週40時間以内であれば、上記2時間分の残業代は発生しないということになります。
なお、1ヵ月単位の変形労働時間制の導入には労使協定又は就業規則の定めが必要です。
次に②ですが、会社と労働者との契約は、簡単に言ってしまえば「〇〇時間の労働に対して〇〇円を支払う。」というものですから、本来、会社は労働者から右の〇〇時間を超える労働を受領する義務を負いません。
したがって、就業規則等で明示的に無許可残業を禁止していれば、原則として、無許可残業について残業代を支払う必要はありません。
但し、労働者が許可を得ないで残業をしていることを知りながら放置したというように、会社の黙認があったと評価できるような場合には、いくら就業規則等に残業許可制を謳っていても、やはり、残業代は支払わなければならなくなります。
③は、労働基準法上、管理監督者には深夜労働による割増賃金以外については割増賃金(残業代)が発生しないと記載されていることから主張できる反論です。
問題は、この管理監督者の範囲です。有名な裁判例があって、管理監督者の範囲はかなり狭く解釈されています。結論から言いますと、Ⅰ:経営者と一体的な立場であり、Ⅱ:重要な職務と権限を与えられており、Ⅲ:賃金等の待遇面で他の従業員に比べて優遇されている人、でなければ管理監督者に当りません。
管理監督者に当たると認定されるケースは極めて限定的ですので、この反論が功を奏することは少ないのが実際のところです。
④は、就業規則等で法定時間外労働があってもなくても一定の残業手当を支払うという制度を採用している場合にする反論です。
この制度は採用している会社は少なくないですが、これについても運用方法を誤ると無効と判断され、結局、会社は残業代を支払わなければならなくなります。
同制度の有効要件は、Ⅰ:法定時間外労働に対する手当であることが明示されていること、Ⅱ:基本給などの他の賃金と明確に区別されていること、Ⅲ:実際の労働時間から残業代を計算したときに固定で支払っている残業手当の額を超えた場合はその差額を支払うようになっていること、です。
たとえば、賃金規程には「営業手当」とだけ書いてある場合はⅠの要件を充たしませんし、給与明細で基本給・各種手当をまとめて「基本給」とだけ表示している場合はⅡの要件を充たしません。そもそも労働時間から残業代を計算すらしておらず差額も支払っていないような場合にはⅢの要件を充たしません。
固定残業代制度は一見会社にとって非常に使いやすい制度のように見えますが、意外とそこまでではないのです。
⑤は有名な「時効」です。残業代の時効は2年です。したがって、残業のあった日から2年が経過すれば時効によって残業代を請求する権利は消滅します。
残業代に限った話ではないですが、時効一般について注意点があります。それは、時効完成後に「承認」してしまうと時効の効果を主張することができなくなってしまうということです。
たとえば、残業から既に2年が経過して時効が完成しているのに、会社が労働者に対して、「今は経営が苦しいからあと1ヵ月は待ってくれ。」などと残業代の請求権を認めた場合、あとで「やっぱり時効だから払わない。」とは言えなくなるわけです。
以上、残業代請求に対する会社の反論について見てきましたが、法定時間外労働がある限り、基本的に会社が残業代の支払いを免れるのは難しいところです。
どうしてもある程度の残業が発生してしまうのであれば、元の賃金を低めに設定して残業代を支払っても経営が成り立つように賃金制度を設計しなければなりません。
ただ、あまりに基本給や他の手当が低いと優秀な人材を確保することができませんので、賃金制度の設計は非常にバランスの難しい問題です。
最後に、原則として会社は労働者との間で定めた労働条件を労働者の不利益に一方的に変更することはできませんので、今から会社の仕組みを変えようと思っても就業規則等を変えるだけでは不十分です。
もし、会社の賃金制度等の変更を検討される場合には、お早めに弁護士へ相談してください。
- メールマガジンバックナンバー
- 第1回メルマガ記事「残業代シリーズ①」 2017.7.27号
- 第2回メルマガ記事「残業代シリーズ②」 2017.8.10号
- 第3回メルマガ記事「残業代シリーズ③」 2017.8.24号
- 第4回メルマガ記事「解雇シリーズ①」 2017.9.14号
- 第5回メルマガ記事「解雇シリーズ②」 2017.9.28号
- 第6回メルマガ記事「企業と保険1」 2017.10.6号
- 第7回メルマガ記事「企業と保険2」 2017.10.24号
- 第8回メルマガ記事「セクハラ・不倫と企業」 2017.11.9号
- 第9回メルマガ記事「セクハラ・不倫と企業2」 2017.12.24号
- 第10回メルマガ記事「個人情報漏洩と企業の損害①」 2017.12.7号
- 第11回メルマガ記事「個人情報漏洩と企業の損害②」 2017.12.21号
- 第12回メルマガ記事「試用期間について」 2018.1.5号
- 第13回メルマガ記事「採用内定について」 2018.1.23号
- 第14回メルマガ記事「債権回収①」 2018.2.8号
- 第15回メルマガ記事「債権回収②」 2018.2.22号
- 第16回メルマガ記事「企業様と交通事故が関連する法的問題①」 2018.3.8号
- 第17回メルマガ記事「企業様と交通事故が関連する法的問題②」 2018.3.22号
- 第18回メルマガ記事「日々業務をする中で」 2018.4.13号
- 第19回メルマガ記事「外国人労働者の雇入れ」
- 第20回メルマガ記事「残業代請求に対する反論①」 2018.5.10号
- 第21回メルマガ記事「残業代請求に対する反論②」 2018.5.24号
- 第22回メルマガ記事「雇用と業務委託(請負)の違いについて」 2018.6.14号
- 第23回メルマガ記事「雇用期間の定めのある契約か否か」 2018.6.28号
- 第24回メルマガ記事「分かりにくい著作権の落とし穴」 2018.7.12号
- 第25回メルマガ記事「社員の給与が差押えされたら…」 2018.7.26号
- 第26回メルマガ記事「会社と労災適用となる交通事故」の関連から「企業コンプライアンス」について」 2018.8.9号
- 第27回メルマガ記事「有給チャンス」 2018.8.23号
- 第28回メルマガ記事「従業員間のトラブルについて」 2018.9.14号
- 第29回メルマガ記事「優良企業は狙われる!?」 2018.10.2号
- 第30回メルマガ記事「有期雇用の活用1」 2018.10.11号
- 第31回メルマガ記事「有期雇用の活用2」 2018.10.25号
- 第32回メルマガ記事「配置転換,出向,転籍について」 2018.11.8号
- 第33回メルマガ記事「配置転換,出向,転籍について②」 2018.11.23号
- 第34回メルマガ記事「事業承継その1」 2018.12.14号
- 第35回メルマガ記事「事業承継その2」 2018.12.28号